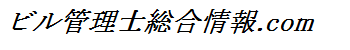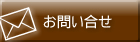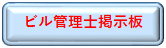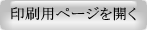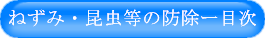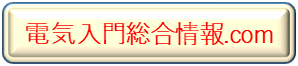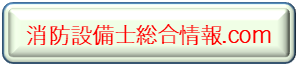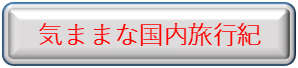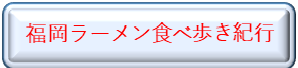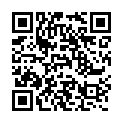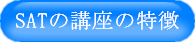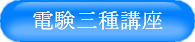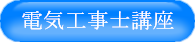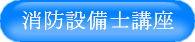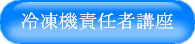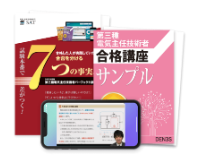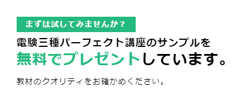ねずみ、昆虫等の防除7
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
ねずみ、昆虫等の防除⑦
防除に用いる機器 < ULV機 < 散粉機 < 煙霧機 < 三兼機 < ライトトラップ < 電撃式殺虫機 < 防除に用いる薬剤 < 油剤 < 粒剤 < 乳剤 < 燻煙剤 < 食毒剤 < 有機リン剤 < 主な有機リン系の殺虫剤 < ピレスロイド剤 < ピレスロイド剤の種類 < 有機リン剤トピレスロイド剤の特徴に注意 < 昆虫成長制御剤(IGR剤) < その他主な薬剤防除に用いる機器と薬剤
防除に用いる機器
ULV機
粒子は5~20μm,高濃度の薬剤を少量処理するのに用いられる。
専用の水性乳剤を、原液のまま、あるいは2~4倍に希釈して使用する。
残留効果は期待できない。
散粉機
そのままの通り、粉剤を散布する機械。
煙霧機
0.1~50μmの粒子を作り出す。室内空間に薬剤を処理する場合に用いる。
蚊やチョウバエの成虫の防除に用いられる。
三兼機
油剤・粉剤・粒剤兼用の散布機である。
ライトトラップ
誘虫灯に誘引された走光性の昆虫をファンの吸引により捕集ネットや粘着シ―トに付着させる。
電撃式殺虫機
走光性のもつ(光に向かう性質を持つ)昆虫の防除に用いる。
3700Aの短波長誘虫灯に引き寄せられた昆虫は22000Vの高圧電流に触れて感電死する。
屋内に害虫を呼び込まないように窓際や出入り口から離して設置する。
防除に用いる薬剤
油剤
油剤は有効成分を灯油(ケロシン)に溶かしたものが多い。
有効成分は1%程度の物が多い。そのまま使用できる便利さがある。
直接散布する空間処理、残留処理以外に煙霧などに用いる。
引火性があるので火気に注意が必要。
粒剤
有効成分を基材に混ぜて粒状にしたもの。水面に浮かせるもの、水中に沈めて使用するものがある。
有効成分がゆっくり溶け出して効果を持続する。
乳剤
原体を有機溶剤に溶かして乳化剤を加えたもので、使用時に水で希釈して使う。
白濁するものが多い。刺激性、引火性は低い。
燻煙剤
ジクロスポスやピレスロイドなど、速効性と致死効力が高い薬剤を助燃剤によって燃焼させ 、煙として屋内に飛散させ、飛翔性昆虫を殺虫する。蚊取り線香など
食毒剤
有効成分を餌材に混合して、食毒(ベイト)として、使用される。
殺虫剤の成分による分類
殺虫剤の成分には有機リン剤、ピレスロイド剤、IGR剤(昆虫成長制御剤)などに分類される。
有機リン剤
- 一度ノックダウンした虫は蘇生することなくそのまま死亡する傾向が強い。
- 比較的速効性で残効性もあり、多くの害虫に有効である。
- 急性毒性が高く、蓄積性、慢性毒性は高くない。
- 有機リン剤には化学構造的に対称型と非対象型が存在する。
- 最近ではイエバエを初め多くの害虫に高い抵抗性が見られる。
主な有機リン系の殺虫剤
- ダイアジノン
- 致死効力、速効性、残効性のバランスが良い。ハエに効力が高い。
- テメホス
- 毒性が極めて低いが蚊幼虫に特異的に有効、他の害虫には効果は低い。
- ジクロルボス
- 蒸気圧が高く常温揮散性が大きい。速効性が極めて高いが残効性に欠けている。樹脂蒸散剤として利用される。
- フェンチオン
- 多くの害虫に有効であるが特に蚊に効力が高い。水中に処理した時の残効性が高い。
- フェニトロチオン
- 日本で開発された対称型有機リン剤で、広範な害虫に有効。特にゴキブリ類に有効である。
ピレスロイド剤
- 除虫菊の有効成分ピレトリンに似た合成物質
- 速効性があり、ノックアウト効果に優れている。(仰天させること)
- いったんノックダウンされた害虫が蘇生することがある。(再び動き出しよみがえる。)
- 忌避性も認められるので、飛翔昆虫や吸血昆虫に対する実用性も高い。
- ピレスロイド剤には追い出し効果(フラッシング効果)がある。
ピレスロイド剤の種類
- フタルスリン
- ノックダウン効果が高く電気蚊取りに多用されている。
- ピレトリン
- 天然の除虫菊の殺虫成分。極めて速効性が高くノックダウンした害虫が蘇生する。
- アレスリン
- 速効性が高く、多くの薬剤に混合して用いられる。
- フェノトリン
- ベルメトリンに類似する。シラミ用で、人体に直接使用できる薬剤がある。
- エンペントリン
- 衣類の防虫剤として紙に含浸させた薬剤がある。
有機リン剤とピレスロイド剤の特徴に注意
上記で述べた通りでその特徴を把握しましょう。
- 有機リン剤は蘇生しない。
- 蘇生するのはピレスロイド剤
- 蘇生とは仰天(ノックダウン)した害虫が再び復活する。
- 有機リン剤には追い出い効果(フラッシング効果)がない。
- ピレスロイド剤には追い出し効果(フラッシング効果)がある。
- 追い出し効果とは薬剤により害虫の棲家から追い出すこと。
上記事柄はしっかり覚えましょう。
昆虫成長制御剤(IGR剤)
IGR剤とはInsect growth regulatorsの略で、昆虫の脱皮を阻害する薬剤で、第4世代の殺虫剤といわれている。
幼虫への速効的な致死効果はない。
その他主な薬剤
- カ―バメ―ト剤
- 有機リン剤と同様の作用を持つ。プロポクスルのみが製剤と許可されている。
- ホウ酸
- 古くからゴキブリの食毒剤として用いられてういる。
- メトキサジアゾン
- ピレスロイド抵抗性チャバネゴキブリに有効。加熱蒸散剤の有効成分に利用されている。
- ヒドラメチルノン
- 効果の発現が遅く、食毒効果が高いのでゴキブリやアリの駆除用食毒剤として用いられている。
薬剤に関するまとめ
良く試験に出題されやすい薬剤の特徴をまとめました。
- ジフェチアロール―――第2世代の抗凝血性殺鼠剤(特定建築物内では使用可能)
- カブサイシン―――忌避剤、かじり防止などの目的
- ブロマジオロン製剤―――動物用医薬部外品(特定建築物内では使用不可)
- クマテトラリル―――第1世代の抗凝血性殺鼠剤
- フィプロニル―――ゴキブリ用の食毒剤
- リン化亜鉛―――1回の経口摂取で致死する。
- フェノトリン―――炭酸ガス製剤
- イカリジン―――吸血害虫用忌避剤
- トランスフルトリン―――常温揮散製剤
- ジクロルボス―――樹脂蒸散剤
- プロペタンホス―――有効成分とするマイクロカプセル(MC)剤
- シリロシド―――1回の経口摂取で致死する。(急性殺鼠剤)
- ワルファリン―――第1世代の抗凝血性殺鼠剤
- フマリン―――第1世代の抗凝血性殺鼠剤
- ディート―――吸血昆虫用忌避剤
- ピリプロキシフェン―――羽化阻害効果
- フタルスリン―――ノックダウン効果
- 第1世代の抗凝血製殺鼠剤は、遅効性で、毒餌を連日(少量を4~5日間)摂取せせることが必要です。
- 第2世代の抗凝血製殺鼠剤は、日本ではジフェチアロールのみが承認されている。
従ってビル管理士試験で第2世代の抗凝血製殺鼠剤といえばジフェチアロールです。
買い物は楽天市場