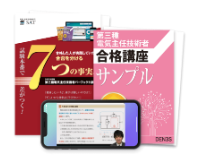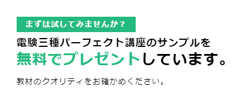計算問題特訓のページ
ビル管理士試験ではよく計算問題の出題があります。
中には計算問題が苦手という方も多くいます。
しかしビル管理士試験の計算問題は電験三種のような複雑な計算は一切ありません。
ある法則を理解していれば解ける問題です。
このページでは繰り返し計算問題を解きどの問題が出題されても対応できるようにしておきましょう。
建築物の環境衛生
空気環境の調整
給水及び排水の管理
清掃
230 x 40買い物は楽天市場
ビル管理士試験ではよく計算問題の出題があります。
中には計算問題が苦手という方も多くいます。
しかしビル管理士試験の計算問題は電験三種のような複雑な計算は一切ありません。
ある法則を理解していれば解ける問題です。
このページでは繰り返し計算問題を解きどの問題が出題されても対応できるようにしておきましょう。
当サイトが運営しているサイトです。
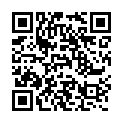
上のQRコ―ドから読み込みができます。
読み込みができない場合は直接下記アドレスからアクセスしてください。
PC、ipad、各種スマ―トフォンなどで学習が可能
ビル管理士試験への最も有効な勉強方法です。