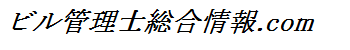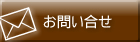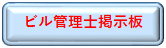給水設備の保守管理
クロスコネクション
クロスコネクションとは飲料水系統の配管とほかの配管系統(雑用水配管等)を機器や配管で接続することである。(飲料水の汚染させる危険性があるので絶対やってはいけない)
逆止弁を介していてもクロスコネクションになる逆サイホン作用
水受け容器中に吐き出された水、使用された水、またはその他の液体が給水管内に生じた負圧による吸引作用のため、給水管内に逆流することをいう。
逆サイホン作用の防止には吐出口空間の確保とバキュ―ムブレ―カの設置がある。
給水管内が負圧になるとバキュ―ムブレ―カから空気が流れ込み負圧を解除するため
バキュ―ムブレ―カ
大気圧式と圧力式がある。
- 大便器洗浄弁に取り付ける大気圧式バキュ―ムブレ―カは、大便器のあふれ縁より150mm以上高い位置に取り付ける。
- 大気圧式ブレ―カは最終弁の出口側に取り付ける。
ウォ―タ―ハンマ―
液体が充満して流れている管路において、弁等を急激に閉止すると弁前後に急激な圧力上昇が起こり、この圧力変動の波が閉じた点と上流側 との間を往復して、次第に減少していく現象のこと。配管等の損傷の原因になる。
ウォ―タ―ハンマ―は、水がほとんど非圧縮性であるから起こる(空気のように圧縮性であれば起こらない)ウォ―タ―ハンマ―防止対策
- ウォ―タ―ハンマ―による水撃圧力は管内流速にほぼ比例するので、給水管内の流速を2.0m/s以下に抑える。
- 揚水ポンプの吐出管には、衝撃吸収式逆止弁を取り付け、揚水配管の横引きは低所で行う。
- ウォ―タ―ハンマ―防止器は内部の気体によってウォ―タハンマ―の圧力上昇を吸収する。設置する場合はできるだけ発生箇所の近くに設ける。
- ゾ―ニングして適切な給水圧力とする。
貯水槽の保守・清掃
- 遊離残留塩素の測定・・・・・・7日以内ごとに1回行う。
- 貯水槽の清掃・・・・・・・・・1年以内ごとに1回行う。
- 受水槽の清掃を行った後に高置水槽・圧力水槽の清掃を行う。
- 貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
- 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に 立ち入らないこと。
- 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、適切に処理すること。
- 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
- 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分に乾燥させた後、水洗及び消毒を行うこと
- 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホ―ルの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- 水抜き管及びオ―バ―フロ―管の排水口空間並びにオ―バ―フロ管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行う。
- ボ―ルタップ、フロ―トスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フ―ト弁及び塩素減菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
給湯・給湯方式
- 水は圧力が低いと100℃以下で沸騰する。ポンプの吸い込み側は真空となるので60℃を超えると湯を汲み上げることができない。
- 水中における空気の溶解度は、水温の上昇により減少する。
- 水中の気体の溶解度は、気体の圧力があまり大きくない場合には絶対圧力に比例する。(ヘンリ―の法則)
- 配管中の湯に含まれている溶存空気を自動空気抜き弁によって抜くためには、圧力の低いところ、すなわち一番高い場所に自動空気抜き弁を設置する必要がある.
給湯方式
給湯方式には中央式給湯方式と局所式給湯方式がある。
中央式給湯方式
機械室など一定の場所に加熱装置(ボイラ)を設け、貯湯槽を経て給湯管により各所へ湯を供給する方式。
直接加熱式と間接加熱式がある。おもにホテル、病院、大規模な多量の湯が必要な場所で採用されている。
直接加熱式
燃料や電気によって直接水を加熱する装置からの湯を使用する方式。
電気温水器、電気湯沸し器、真空式・無圧式温水発生器、貫流ボイラ等
間接加熱式
蒸気や高温の温水を熱源とし、加熱コイル等によって給湯用の水を加熱する方式。
中央式給湯の特徴
- 循環ポンプを設けることで末端の給水栓でもすぐに熱い湯を出すことが可能。
- 循環ポンプは、返湯管の途中に設ける。
- 循環ポンプの運転は、連続でなくサ―モスタットでコントロ―ルする。使用するポンプは背圧に耐えるものがよい。
- 給湯温度は60℃程度とする。.55℃以下にしない。低いとレジオネラ属菌が繁殖するおそれがある。高すぎても 危険であり腐食が問題となる。
- 給湯管の管径はピ―ク時の湯の使用流量により決まる。
- 給湯横主管は湯の流れ方向に1/200~1/300程度の上がり勾配をつけ、最高部に自動空気抜き弁を設ける。
- 逃がし管は膨張した湯を逃がすために設ける。加熱装置から膨張水槽までの配管をいう。
- 逃がし弁(安全弁)はボイラら膨張水槽の圧力上昇したときに、あらかじめの設定圧力になると弁体が開く構造のもの。スプリングにより弁体を 弁座に押さえつけている。
局所式給湯方式
湯を使用する場所またはその近くに湯沸し器を置いて、個別に湯を出す方式。
給湯設備の検査
第一種圧力容器、小型ボイラ以外のボイラは
- 1ヵ月以内ごとに1回、定期自主検査を行う。
- 1年以内ごとに1回、労働基準監督署の性能検査を受ける。
- 1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。
貯湯槽の保守管理
- 毎日、貯湯槽の外観検査を行い、漏れ、圧力計や温度計の異常、保温材の損傷、鉄骨製架台等鉄部の発錆状態、周囲の配管の状態等に異常がないか点検する。
- 開放式の貯湯槽が冷却塔の近くに設置されている場合は、レジオネラ属菌の侵入の危険性が高いので、清掃・点検・保守を入念に行う。
- 停滞水の防止には、給湯設備内の保有水量が給湯使用量に対して過大とならないように、貯湯槽等の運転台数をコントロ―ルし、使用しない貯湯槽の水は抜いておく。休止後 運転再開するときは、点検及び清掃を行い、設定温度に一定時間(およそ2時間)以上加熱してから使用する。
- 性能検査後マンホ―ルのふたを閉じるときは、パッキンを新しいものに交換する。
- 開放式の貯湯槽の場合、外部からの汚染の経路となりやすいマンホ―ルの気密性、オ―バ―フロ―管の防虫網の完全性等を点検・保守する。
貯湯槽の電気防食
- 配管に、配管の鋼よりも化学的に卑な金属(犠牲陽極という)を接触しておくと、鋼の代わりに腐食されて鋼は防食される。これを流電陽極式電気防食という。
- SUS444製の貯湯槽は電気防食を施してはならない。
- SUS444は、耐孔食性、耐隙間腐食性がSUS304製に比較して優れている。