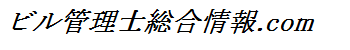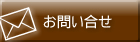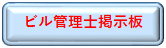この法律は、 労働基準法 と相まって、労働災害の防止 のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康 を確保する とともに、快適な職場環境 の形成と促進することを目的とする。
事務所衛生基準規則
- 気積(容積)は労働者1人について、設備の占める容積及び4mを超える高さにある空間を除き10 m3以上
- 一酸化炭素濃度は100万分の50 以下
- 二酸化炭素濃度は100万分の5000 以下
- 事業者は、室の気温が 10 ℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 空気調和設備、機械換気設備 を設けている場合はビル管理法と同じ基準に適合するようにしなければならない。
- 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものは除く)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇 その他の換気のための設備を設けなければならない。 事業者は、燃焼器具 を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
室の作業面の照度
- 一般的な事務作業・・・・・ 300 lx以上
- 付随的な事務作業・・・・・ 150 lx以上
トイレの数
便所は男子と女子と区別する。同時に就業する労働者の人数により、便器の数が決められている。
男性トイレ・・・大便器は60 人ごとに1個以上、小便器は 30 人ごとに1個以上女性トイレ・・・大便器は20 人ごとに1個以上
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩 の設備を設けるように努めなければならない。
環境基本法
この法律は環境の保全 について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者 及び国民の責務 を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活 の確保に寄与 するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
公害の定義 環境基本法で定義されているものは以下の7つである。
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
大気汚染物質の基準
- 二酸化硫黄
- 時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であること。
- 一酸化炭素
- 1時間値の1日平均値が10 ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下であること。
- 浮遊粒子状物質
- 1時間値の1日平均値が0.10 mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m3以下であること。
- 光化学オキシダント
- 1時間値が0.06 ppm以下であること。
- 二酸化窒素
- 1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾ―ン内又はそれ以下であること。
浄化槽法
この法律は、浄化槽 の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽 工事業者の登録制度 及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士 及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域 の水質の保全 等 の観点から浄化槽による し尿 及び雑排水 の適正な処理を図り、もって生活環境 の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
浄化槽の管理
- 浄化槽の管理者は、毎年1 回、指定検査機関の水質検査を受ける。
- 処理対象人数が501 人以上の浄化槽では、技術管理者を置く。
水質汚濁防止法
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、 生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の 防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して 人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
大気汚染防止法
この法律は、工場及び事業者における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施 を推進し、並びに自動者排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、 国民の健康を保護するとともに 生活環境を保全し、並びに大気の汚染に 関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
騒音規制法
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音 に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
悪臭防止法
この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、 生活環境を保全し、国民の健康の保護,に資することを目的とする。
特定悪臭物質
不快な臭いが原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質をいう。
- アンモノア
- メチルメルカプタン
- 硫化水素
- 硫化メチル
- トルエン
- "アセトアルデヒド
旅館業法、興行場法、理容師法など(生活衛生関係営業法令)
- 興行場法
- 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポ―ツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設
- 旅館業法
- 旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業及び下宿営業をいう。
- 公衆浴場法
- 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 食品衛生法
- 食品衛生法で定める営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売することをいう。
入場者の衛生に必要な措置
- 興行場法
- 営業者、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を 講じなければならない。
- 旅館業法
- 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の 衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 公衆浴場法
- 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔、その他 入浴者の衛生及び風記に必要な措置を講じなければならない。
営業に関して都道府県知事に届け出なければならないもの
- 理容師法
- 美容師法
- クリ―ニング業法
健康増進法の目的(第一条)
この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進 の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の 改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
平成30年の健康増進法の改正では受動喫煙の防止の強化が行われ、原則として、学校・病院・児童福祉施設での敷地内の禁煙の徹底が図られている。
健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について
特定施設は「第一種施設」、「第二種施設」、「喫煙目的施設」に分けられる(法第28条)。この区分に従い、禁煙や受動喫煙防止等の処置が規定されている。
第一種施設は、子どもや患者等に特に配慮が必要な施設
- 学校
- 児童福祉施設
- 病院・診療所
- 行政機関の庁舎等
第ニ種施設は第一種施設以外の施設
- 事務所
- 工場
- ホテル、旅館
- 飲食店
- 旅客運送用事業船舶、鉄道
- 国会、裁判所等
ただし、ホテルの客室など、人の居住の用に供する場所は適用外とされる。
「第二種施設」において喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要になる。
なお、経過措置として、既存の経営規模の小さい飲食店(個人又は中小企業が経営する客室面積が100m2以下のもの)は、別に法律を定める日まで、標識を掲示することで喫煙可能とされている。
喫煙目的施設
喫煙目的施設は喫煙可能であるが、喫煙を主目的とするバーやスナック、公衆喫煙所などに限定される。
- 喫煙を主目的とするバ―、スナック等
- 店内で喫煙可能なたばこ販売店
- 公衆喫煙所
ただし、喫煙可能部分には、
- 喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
- 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。